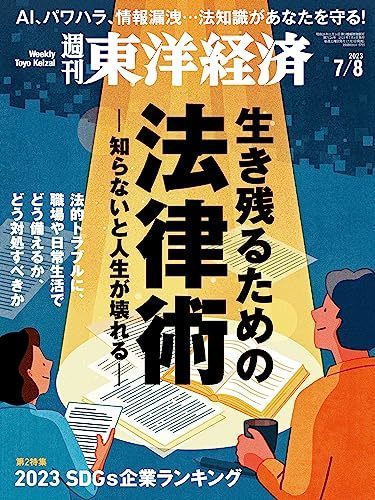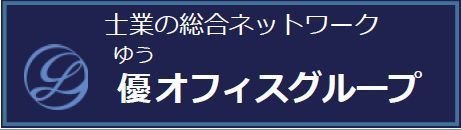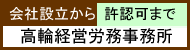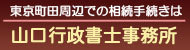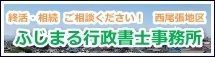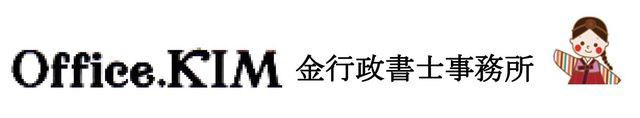相続手続代行・終活支援のことなら、東京・名古屋・横浜・さいたまの優オフィスグループにお任せください。
初回相談無料
お気軽にお問合せください
0120-928-714
遺言書を見つけ出す方法
もともと故人から「遺言書を作成している」と聞いていたのですが、一体どこにあるのかわかりません。どのように探せばよいのでしょうか?
遺言書がどこにあるのか、
実は役所で遺言書を探し出す方法というものが2つあります。
一つ目が公証役場で故人様の作成した公正証書遺言または秘密証書遺言がないか確認する方法、二つ目が法務局で故人様の自筆証書遺言が保管されていないか確認する方法です。この二つの方法についてさらに詳しく見てみたいと思います。
公証役場で遺言書の有無を捜索する
一つ目の、公証役場で故人様の公正証書遺言等が作成されていないか確認する方法ですが、最寄りの公証役場に出向き、「公正証書遺言等登録検索システム」を利用、その故人様が公正証書遺言あるいは秘密証書遺言を作成していたかどうか確認するというものです。もし公正証書遺言が作成されていた場合、その公正証書が作成された公証役場と作成年月日、証書番号、作成を担当した公証人名などを教えてもらうことができます。この「公正証書遺言等登録検索システム」ですが、もちろん誰でも照会できるというわけではなく、基本的には故人様亡き後、法定相続人の立場の方が照会請求を行うことができます。
また、この照会請求は、代理人からも可能であり、その場合には、法定相続人の方から実印捺印のある委任状と印鑑証明書を添付することが必要となります。なお、照会手数料は不要です。
<公正証書遺言等登録検索システム照会請求の際に必要な書類>
※ 法定相続人の一人が照会請求を行う場合
請求先 | 全国の公証役場 |
必要書類 | 被相続人の死亡記載の除籍謄本 請求する相続人と被相続人との相続関係を証する戸籍謄本 相続人の本人確認資料 <代理人からの請求の場合には、次の書類も必要> 相続人からの委任状 相続人の印鑑証明書 代理人の本人確認資料 |
請求費用 | 無料 |
照会した結果、故人様の公正証書遺言があった場合には、その遺言書が保管されている公証役場に対して改めて公正証書遺言謄本交付請求を行うことにより、実際に作成された公正証書遺言の内容を確認する流れとなります。
公正証書遺言謄本交付請求の手続きの詳細としては次のとおりです。
<公正証書遺言謄本交付請求の際に必要な書類>
※ 法定相続人の一人が照会請求を行う場合
請求先 | 公正証書遺言が保管されている公証役場 |
必要書類 | 被相続人の死亡記載の除籍謄本 請求する相続人と被相続人との相続関係を証する戸籍謄本 相続人の本人確認資料 該当の公正証書遺言の特定ができる資料 (公正証書作成日、担当公証人、公正証書番号等) <代理人からの請求の場合には、次の書類も必要> 相続人からの委任状 相続人の印鑑証明書 代理人の本人確認資料 |
請求費用 | 謄本1ページにつき250円×ページ数分 |
ここでご注意いただきたいのが、この公正証書遺言謄本交付請求は、どこの公証役場で請求してもよいわけではなく、その遺言書の原本が保管されている公証役場に直接出向いて請求することが原則として必要となります。
ただ、その公証役場が遠方にある場合には、郵送での請求も可能です。公正証書遺言謄本交付請求を郵送で行う場合には、請求先となる公証役場に事前に連絡をして郵送手続きについての段取りを確認したうえで行うことをお勧めします。ちなみに、公正証書遺言謄本交付請求を郵送により行う場合には、戸籍謄本等の原本を郵送することになりますが、原本と併せて原本証明をしたコピーを同封することで戸籍謄本の原本を返却してもらうことが可能です。
遺言書がどこにあるのか捜索するというのは、ことのほか骨の折れるものです。また、本当に遺言書を作成していたのか否か、多大な不安と心労がつきまとうものです。当事務所では、公証役場での公正証書遺言の有無の調査をはじめ遺言捜索を支援しております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
まずはお気軽にお問合せ下さい!!

初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
次に、法務局で故人様の自筆証書遺言が保管されているかどうか確認する方法について解説します。こちらは、令和2年から始まった自筆証書遺言を法務局に預かってもらえる「法務局における自筆証書遺言保管制度」を利用して故人様がどこかの法務局に自筆証書遺言を預けているかどうかを確認するものです。実際の手続き方法としては、最寄りの法務局(遺言書保管所)に、遺言書保管事実証明書の交付請求をすることによって行います。この請求を行うことにより、法務局に保管されている遺言書の有無、遺言書が保管されている場合には、遺言書が保管されている法務局(遺言書保管所)、遺言書の作成年月日、遺言書の保管番号などが判明します。
<遺言書保管事実証明書交付請求手続>
※ 法定相続人の一人が照会請求を行う場合
請求先 | 全国の遺言書保管所 |
必要書類 | ① 請求書(法務局所定の様式のもの) ② 被相続人の死亡事実を確認できる戸籍(除籍)謄本 ③ 請求人が相続人であることを証する戸籍謄本 ④ 請求人の住民票の写し ⑤ 請求人の請求人の顔写真付き本人確認資料 |
請求費用 | 800円 |
注意点としては、全国のどの遺言書保管所でも交付請求が可能なので、最寄りの遺言書保管所となっている法務局で手続きを行えばよいのですが、法務局の全てが遺言書保管所となっているわけではないので、手続きを行おうとする法務局が遺言書保管所となっているかどうか法務省のホームページで事前に確認してから手続きを行うことをお勧めします。
遺言書保管所となっている法務局
https://www.moj.go.jp/MINJI/07.html
請求方法は窓口か郵送か、いずれかの方法で行うことができます。窓口の場合は、事前予約が必要なこと、委任状等に基づき任意代理人が請求することはできず、基本的には請求人たる相続人本人が出頭して請求することが必要となります。その際、マイナンバーカードなどの請求者本人の顔写真付き身分証明書が必要になりますのでご注意ください。
郵送の場合は、先ほど説明した必要書類を郵送、不備がなければ数日から1週間程度で遺言書保管所から請求者本人の住民票上の住所あてに遺言書保管事実証明書が郵送されます。ちなみに、公正証書遺言謄本交付請求を郵送で行う場合と同じように、戸籍謄本等の原本を郵送することになりますが、原本と併せて原本証明をしたコピーを同封することで戸籍謄本の原本を返却してもらうことは可能です。
遺言書保管事実証明書を取得して、遺言書有りの結果だった場合には、改めて法務局(遺言書保管所)に対し、遺言書情報証明書の交付請求手続きを行うことにより、遺言書の内容確認が可能となります。この遺言書情報証明書をもとにその後の遺産名義変更などの遺言執行を行っていくことになるのですが、この交付請求手続きが意外と面倒なので注意が必要です。
ちなみに、先に説明した遺言書保管事実証明書交付請求手続きと同様に、窓口か郵送かで手続きを行うこと、窓口の場合には、請求者本人が出頭する必要があることなどは同様です。
<遺言書情報証明書交付請求手続>
請求人 | 関係相続人等(遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者など) |
請求先 | 全国の遺言書保管所 |
必要書類 | ①請求書(法務局所定の様式のもの) ②遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本 {C}③ その他遺言者と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本 {C}④ 相続人全員の戸籍謄本及び住民票 {C}⑤ 相続人住所記載の法定相続情報一覧図(これを添付すれば②~④省略可) ⑥ 請求者の顔写真付き本人確認資料 |
請求費用 | 交付請求1,400円 |
遺言書情報証明書交付請求は、上記の必要書類からもおわかりかと思いますが、被相続人の法定相続人全員を特定するための戸籍謄本を全て取り揃える必要があること、法定相続人全員の住民票等の書類が必要となることなど、遺言書情報交付請求を行うために必要な書類を取り揃えることが非常に大変であるということを知っておく必要があります。
また、遺言書情報証明書の交付が相続人の一人になされると、「関係遺言書保管通知」という、交付請求を行った方以外の他の法定相続人全員、その遺言書に記載された受遺者及び遺言執行者に被相続人の遺言書が存在していることの通知が法務局よりなされることになりますのでご留意ください。
遺言書がどこにあるのか捜索するというのは、ことのほか骨の折れるものです。また、本当に遺言書を作成していたのか否か、多大な不安と心労がつきまとうものです。当事務所では、公証役場での公正証書遺言の有無の調査をはじめ遺言捜索を支援しております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
まずはお気軽にお問合せ下さい!!

初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
優オフィスグループ主要メンバーのご紹介

東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優

名古屋オフィス
責任者 行政書士 冨川誠太

東京・品川オフィス
責任者 行政書士 三雲琢也

さいたまオフィス
責任者 行政書士 渡辺典和

横浜北オフィス
責任者 行政書士 深野友和

横浜南オフィス
責任者 行政書士 小幡麻里