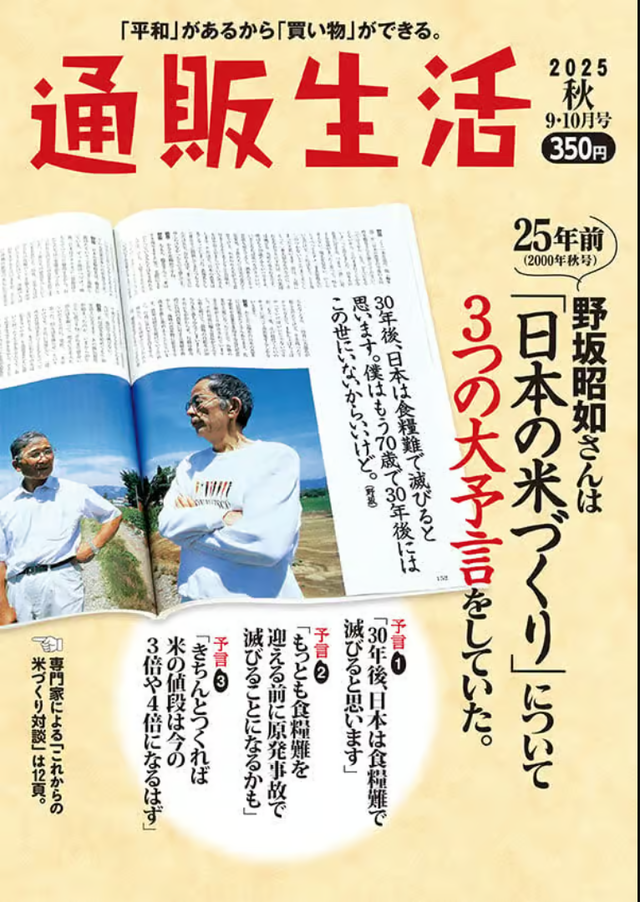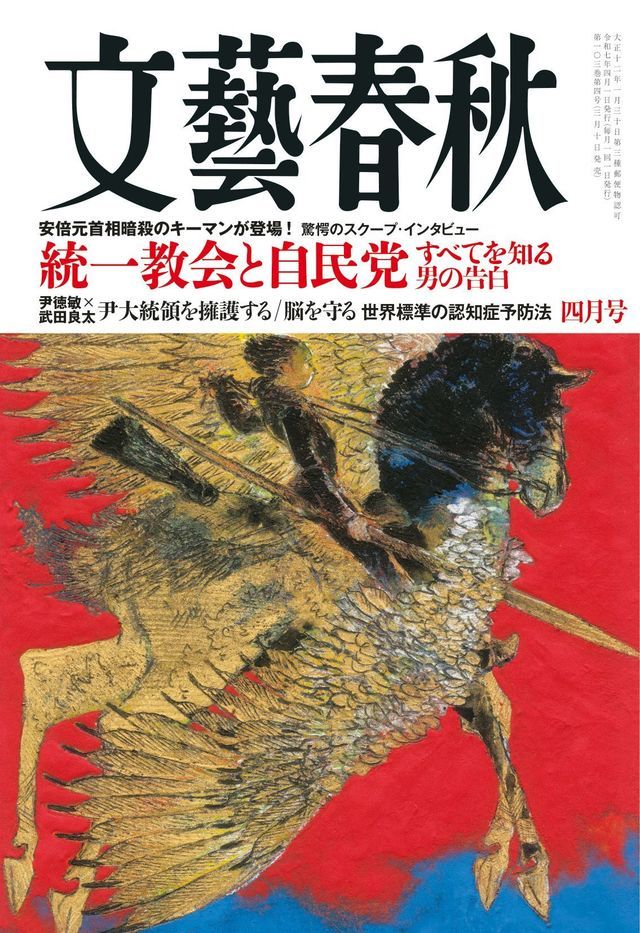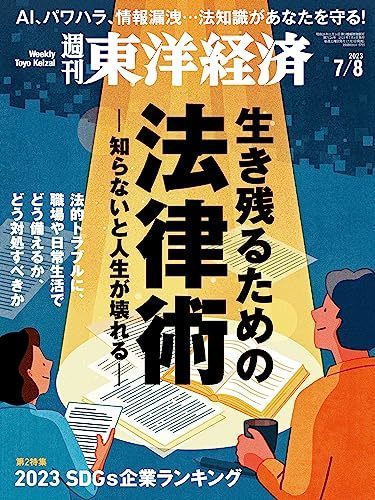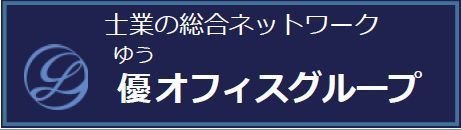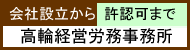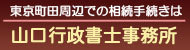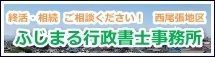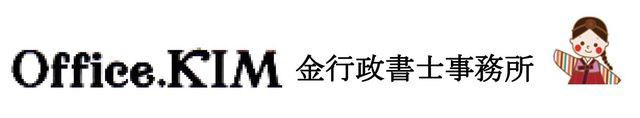相続手続代行・終活支援のことなら、東京・名古屋・横浜・さいたまの優オフィスグループにお任せください。
初回相談無料
お気軽にお問合せください
0120-928-714
自筆証書遺言が見つかった場合どうする?
遺言の検認手続きについて知っておこう
故人が自筆証書遺言を作成していましたが、この遺言書で相続手続きを進めるには検認手続きが必要になると銀行から言われてしまいました。遺言の検認手続きはどのように進めていけばよいのでしょうか?
自筆証書遺言があった場合、その遺言書をもとに相続手続きを進めるためには、家庭裁判所にて検認手続を経る必要があります。
これは、実務上、検認手続きを経ていない自筆証書遺言では、相続登記などの遺産名義変更や預貯金解約払戻などの手続きを受付けてもらえないといったことがあるためです。但し、自筆証書遺言を法務局に預けていた場合、並びに公正証書遺言の場合には、検認手続を経ずに遺言による遺産名義変更手続きは可能となります。
必要書類を取り揃えて家裁に自筆証書遺言の検認を申立てる
自筆証書遺言の検認手続きには、必要書類を取りそろえて、管轄の家庭裁判所に自筆証書遺言検認申立てを行うことが必要になります。
具体的には、法定相続人全員を特定できる戸籍資料を収集、法定相続人の現在戸籍謄本も収集することが必要になりますが、これがことのほか大変で、申立ての必要書類を集めるだけでも膨大な時間と労力がかかることを知っておく必要があります。
特に、兄弟姉妹が法定相続人となるようなケースでは、収集すべき戸籍の量も膨大となり、法定相続人の数にもよりますが、申立てに必要な戸籍資料の準備だけでも1カ月かそれ以上かかる場合がありますので注意が必要です。
必要書類が取り揃ったら、管轄の家庭裁判所に必要書類を提出、検認申立を行うことになります。
<自筆証書遺言の検認申立手続き>
申立人 | 遺言の保管者または遺言書を発見した相続人 |
申立先 | 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立の 必要書類 | ①申立書 ②遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本 ③相続人全員の戸籍謄本 ④その他遺言者と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本 ⑤相続関係説明図 ⑥法定相続情報一覧図(添付した場合、②~⑤は原則として省略可) ※事案により上記以外の資料が必要な場合あり |
申立費用 | 収入印紙 800円+切手代 |
自筆証書遺言の検認手続きは、必要となる相続関係を特定する戸籍収集が必要となるなど、ことのほか骨の折れるものです。また、故人様亡き後の心身ともに疲弊した中でのお手続きというのは、ことのほか大変なものです。
当事務所では、申立てのために必要となる戸籍収集を始め遺言書の検認手続きを支援しております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
まずはお気軽にお問合せ下さい!!

初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
検認の申立ての後、検認期日を決定、法定相続人を呼び出す
検認申立が受理されると、検認期日(実際に遺言書を開封、内容の確認をする日のこと)が設定され、遺言書の発見者または保管者たる検認手続きの申立人をはじめ、遺言者の法定相続人にその遺言の存在と内容を明らかにする手続きへと進みます。
家庭裁判所は、検認手続きの申立人と日程を調整して、検認期日をいつにするか決定、法定相続人全員に対し検認期日に出頭するよう文書で通知します。
私の経験では、検認申立てから検期日まで、約1~2カ月の時間を要することになるので注意が必要です。
検認期日当日ですが、基本的には検認手続きの申立人が、その保管している自筆証書遺言を持参、他の法定相続人についても呼び出しを受けていますので、通常は検認手続きの申立人と他の法定相続人とが一堂に会する場において、検認手続きが実施されることになります。検認手続きでは、担当の書記官が自筆証書遺言を開封してその内容を読み上げるとともに、実際に検認手続きに立ち会った相続人当事者にその遺言書を提示して内容の確認を行います。
その後、遺言書の原本の末尾に「検認調書」という書面が合綴され、これをもって検認済みの自筆証書遺言となり、一連の検認手続きが終了します。
ちなみに、法定相続人が全員揃っていなくても、これらの検認手続きは実施されますのでご留意ください。
この手続きを経てようやく「検認済み自筆証書遺言」となって、不動産の相続登記や預貯金の解約払戻等の相続手続きがこの遺言書に基づいて可能となります。
封印のなされた遺言書は検認期日に開封することが必要
その他の注意点として、封印のなされた自筆証書遺言は必ず家庭裁判所の検認手続きの場で開封されることが必要で、これに違反すると5万円以下の過料(行政法上の罰金)が科せられるとされていることになっていますので、封印されている遺言書を勝手に開封しないように注意しましょう。
検認手続きは遺言の有効無効の判断の場ではない
検認手続きは、自筆証書遺言の存在と内容の確認を目的に行われるものであり、その遺言の有効か無効かの判断がなされる場ではありません。従いまして、検認手続きがなされた遺言書だからといってその遺言書の内容自体が有効である、といった確認がなされるわけではない、ということも併せて認識をもっておかれるとよいと思います。
ここまで、自筆証書遺言の検認手続きの中身について詳しく見てきましたが、検認手続きというのが、申立てまでの準備が大変であったり、申立ててから検認実施までに多大な時間を要すること、封印のなされた遺言書の開封は検認手続きまで待たなければならず、内容の確認に時間がかかることなど、デメリットも大きいと言わざるを得ません。
そこで、もしできることなら、このような検認手続きを行わずに相続手続きを進められる公正証書遺言の方法で遺言書を作成されるか、もしくは、自筆証書遺言で作成する場合でも法務局に預けておくなど、検認手続きを経なくても遺言執行ができるようにしておくことをお勧めします。
自筆証書遺言の検認手続きは、必要となる相続関係を特定する戸籍収集が必要となるなど、ことのほか骨の折れるものです。また、故人様亡き後の心身ともに疲弊した中でのお手続きというのは、ことのほか大変なものです。
当事務所では、申立てのために必要となる戸籍収集を始め遺言書の検認手続きを支援しております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
まずはお気軽にお問合せ下さい!!

初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
優オフィスグループ主要メンバーのご紹介

東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優

名古屋オフィス
責任者 行政書士 冨川誠太

東京・品川オフィス
責任者 行政書士 三雲琢也

さいたまオフィス
責任者 行政書士 渡辺典和

横浜北オフィス
責任者 行政書士 深野友和

横浜南オフィス
責任者 行政書士 小幡麻里