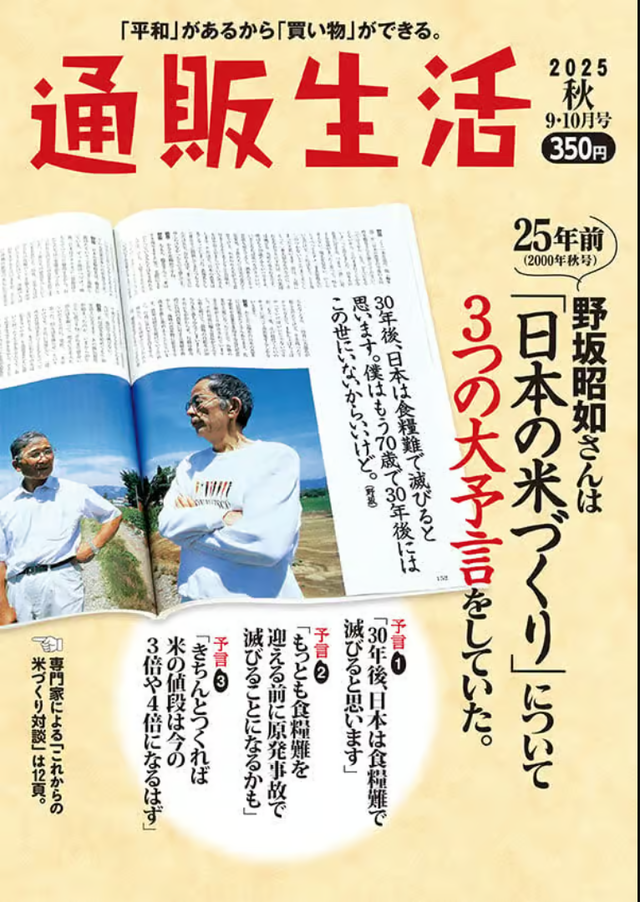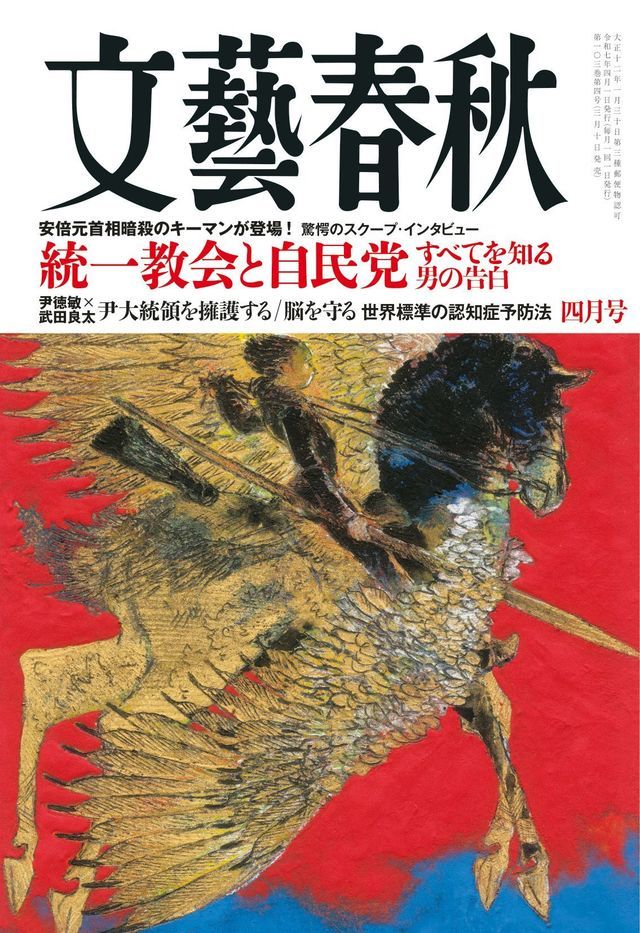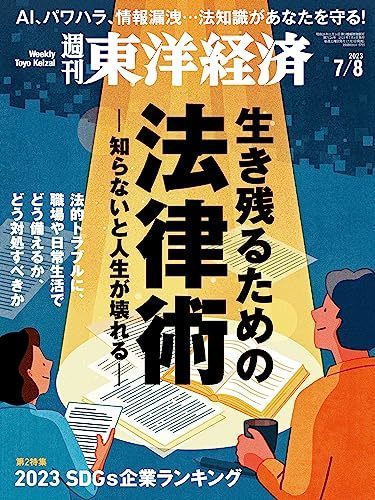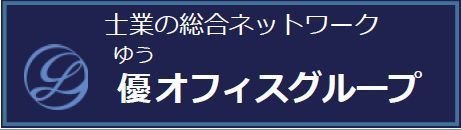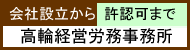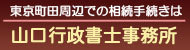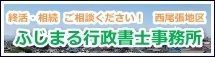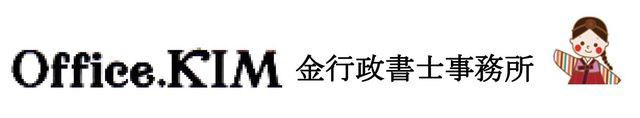相続手続代行・終活支援のことなら、東京・名古屋・横浜・さいたまの優オフィスグループにお任せください。
初回相談無料
お気軽にお問合せください
0120-928-714
お墓について
お墓を引っ越す「改葬」の手続きについて
先祖の墓が地方にあるが、自分達は都会に住んでいてなかなかお墓参りに行けない。そんな時、お墓を引越す「改葬」という方法があります。改葬は、墓地にある遺骨全部を新しい墓地に移動することになります。
新しい墓地の墓石については、古い墓石ごと新しい墓地に移動させて使用する方法と、古い墓石を撤去し廃棄処分したうえで、新しい墓地に新しく墓石を建てる方法があります。前者は、移動のコストがかかり、後者は、古い墓石の撤去・廃棄処分費用及び新しい墓石代のコストが、工事費用と別にそれぞれかかります。
改葬には、行政の許可が必要で、必要書類の手配等の手順を踏んで手続を行う必要がありますし、なにより、これまでお付き合いのあったお寺の菩提寺に対して、改葬の必要な事情などについて誠意をもって事前に話をする配慮が大切です。
なお、墓地の中の遺骨の全部ではなく一部を移動する「分骨」という方法があり、こちらは改葬と違い行政の許可までは必要はありませんが、菩提寺などお墓の管理者に事前に話し合い了承を得て「分骨証明書」の取得が必要です。また、分骨の際の遺骨の取り出し等で石材店の手配と費用が必要です。
改葬の流れと手続き
 移転先の墓地を決定する
移転先の墓地を決定する

 移転先の墓地に永代使用料と管理料を納付し、永代使用許可証の発行を受ける
移転先の墓地に永代使用料と管理料を納付し、永代使用許可証の発行を受ける

 既存の墓地のある市区町村役場発行の「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、既存の墓地管理者から捺印をもらう
既存の墓地のある市区町村役場発行の「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、既存の墓地管理者から捺印をもらう

 改葬許可申請書と永代使用許可証(受入証明)を提出し、改葬許可証の発行を受ける
改葬許可申請書と永代使用許可証(受入証明)を提出し、改葬許可証の発行を受ける

 改葬許可証と永代使用許可証を移転先の墓地へ提出
改葬許可証と永代使用許可証を移転先の墓地へ提出

 改葬のための供養や抜魂式を執行し遺骨を搬出。移転先へ搬送
改葬のための供養や抜魂式を執行し遺骨を搬出。移転先へ搬送

 移転先の墓地管理者に納骨日時を連絡のうえ、納骨
移転先の墓地管理者に納骨日時を連絡のうえ、納骨
改葬にはまとまった費用が必要
改葬をするには、「墓地、埋葬等に関する法律(略して墓埋法)」の規定により市区町村役場の許可が必要です。この許可申請には、「永代使用許可証」と「改葬許可申請書」が必要です。永代使用許可証は移転先の墓地に永代使用料と管理料を支払えば、墓地管理者より発行してもらえますが、火葬許可申請書には必ずもとのお墓の管理者であるお寺の住職様等からの承諾の捺印が必要です。一方で檀家だったお寺から改葬をする際に、「離檀料」と称して費用の支払いが必要になると見聞することがあったのですが、私自身が改葬の手続きをしたとき、いわゆる離檀料を支払った記憶はありません。そこで、知り合いのご住職さん何名かに聞いてみると、口を揃えてそもそも離檀料というものはないとのことでした。ただ、ご住職さんとお話をしていてみえてきたのは、それまでに菩提寺が親族に代わって墓地の管理を永年してきたような場合、檀家としてはやはり菩提寺に対する御礼として何らかの配慮が大切なのだと感じます。
改葬には、旧墓の撤去費用、新墓の墓石代や施工費、骨出しや納骨の際のお布施など諸費用が必要となり、一般的には合計およそ200万円は必要であるといわれています。改葬の際には相当の費用がかかることをあらかじめ覚悟しておいたほうがよいでしょう。
改葬には、元の墓地の撤去費用や法要費用、新しい墓地の永代使用料や管理料、新しくお墓を建てる際は、墓石購入費用などがかかります。
また、改葬にあたり、元のお墓の所在地の市町村で「改葬許可」を得る必要があり、改葬許可申請の際、元の墓地管理者であるお寺から、改葬についての承諾の捺印をもらう必要があります。元々、お付き合いのあったお寺を離れて、お墓を移す際には、お寺に対して事前に相談し、改葬の必要な事情とこれまでお世話になったお寺へ誠意をもって対応し、円満に改葬手続きが進むように十分に配慮する必要があります。
当事務所では、改葬許可申請の代行、改葬の前提となる墓地管理者との打合せの代行など、改葬の手続きを円満、円滑に進むお手伝いをいたします。初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
まずはお気軽にお問合せ下さい!!

初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
新しいお墓を購入するとき気を付けたいポイント
入るお墓を購入するといっても、お墓の種類やタイプは、実は様々です。墓地の使用権を取得し、そこに墓石を建てる、従来から一般的にある「お墓」を購入し、そこに入る方法と、従来のお墓の形にとらわれない、新しいタイプの納骨方法を選択する方法の大きく2つに分かれますが、まずは、従来型のお墓についてみていきましょう。
従来型の墓地は3種類
従来型の墓地の種類は大きく分けて、「寺院墓地」「公営墓地」「民営墓地」の3種類があります。
「寺院墓地」は、寺院が運営する墓地で、一般的に宗派による制限があります。また、管理する寺院により、寺院の檀家になることを条件とする場合と檀家にならなくてもいいが、墓前の法要の際には、他の寺院の僧侶を制限することが多いのが特徴です。石材店は指定がある場合と自由に選べる場合とが混在しています。
「民営墓地」は、宗教法人や公益法人等が運営する墓地で、宗教や居住地等の使用制限はありません。ただし。お墓を建てる際に石材店が指定されているのが一般的です。
「公営墓地」は、地方自治体が運営する墓地で、居住地や遺骨の有無により、使用の制限があります。ただ、石材店は自由に選ぶことができます。
墓地の種類と特徴
タイプ | 寺院墓地 | 公営墓地 | 民営墓地 |
運営 主体 |
寺院
|
地方公共団体
| 形式上宗教法人や公益法人が主体となるが実質的には民間業者が運営する形態 |
費用
|
比較的高い
|
比較的安い
|
比較的高い |
供給量
|
それほど多くない |
首都圏では少ない |
多い |
場 所
| 都心であれば街中に多く、交通の便が良い | 古い所は都心に近いが 新規開発された所は郊外 が多い | 大規模開発された所は 郊外が多い
|
区画の広さ | 寺によりさまざま
| 3~6㎡(東京都)
| 都心部で1~2㎡が多い
|
宗 派
| 檀家に限られるが最近では宗派不問も増えている |
宗派不問 |
宗派不問 |
墓石の購入
|
門前の石材店指定が 多い
|
石材店不問
|
石材店指定が多い
|
その他の制限
|
宗派不問の場合でも法要等は宗派に則る
|
原則居住していること、遺骨を所持していることが必要
|
寺院所有の場合、法要等は宗派に則る
|
気になるお墓のお値段は?
入るお墓がない方の第一の選択肢として、新しいお墓を建てる、ということがあります。その際のお墓の費用には、「墓石建立費」、土地の使用料である「永代使用料」、「管理料」が必要になります。
墓石建立費は石代と工事費からなり、一般的な相場は70万円~200万円ですが、石代は石の種類や大きさ、デザイン、刻字によっても値段が大きく異なります。
永代使用料は、墓地を利用する際に、最初に支払う使用料のことで、1平方メートルあたりで規定されます。墓地は、所有するのではなく、あくまでも永代にわたり霊園から墓地を使用する権利を認めてもらう形態になるため、墓地の使用料として支払うことになります。一般的には、寺院墓地、民営墓地のほうが高く、公営墓地のほうが割安で、どの種類の墓地でも立地と広さにより費用に大幅な開きがあります。
管理料は、霊園を管理する費用で、永代使用料と同じく1平方メートルあたりで規定され、広さに応じた金額を毎年1回、年間の管理料として支払うケースが多くなっています。管理料も寺院墓地、民営墓地が高めで、公営墓地のほうが割安の傾向があります。
新しくお墓を建てた場合、通常、開眼法要を行います。実際にお墓を建てた後、納骨の際には、埋蔵のたび、「埋葬許可証」の発行を火葬場より受け墓地購入時にもらう「墓地使用許可書」を提示するという手続きを行います。埋蔵の手順として、まず日取りを事前に墓地管理者へ連絡し、墓石の一部である香炉や目地、拝石などを外して納骨する必要があり、構造上石材店の手配を必要とすることがあります。埋蔵費用は地域差がありますが、2~3万円が一般的な相場といわれています。
お墓にかかる費用
種別 | 費用項目 | 平均金額 | 支払先 | |
改葬費用 |
| 離檀料 | 0~数十万円 | もとの菩提寺 |
閉眼法要 | 3~5万円 | 僧侶 | ||
墓石解体・撤去費用 | 30万円~100万円 | 石材店 | ||
墓地購入費用 | 墓石費用及び工事費用 | 70~200万円 | 石材店 | |
永代使用料 寺院墓地 民営墓地 公営墓地 | 1㎡あたり 25~70万円 20~100万円 20~70万円 |
新墓地管理者
| ||
開眼法要 | 3~5万円 | 僧侶 | ||
ランニ ング コスト | 管理料(年間) 寺院墓地 民営墓地 公営墓地 |
数千~数万円(御布施含む) 数千~数万円 0~1万円 |
墓地管理者
| |
※ 金額は一般的な目安であり、地域によっても変わってきますので、これよりも上下限する場合があります。
まずはお気軽にお問合せ下さい!!

初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
失敗しないお墓選びのポイント
お墓を選ぶポイントは2つ。1つはどの場所に墓を造るかの選定、もう一つはどのような墓にするか、墓石の選定です。
まず、お墓の場所をどこにするかについて「寺院墓地」「公営墓地」民営墓地」のどの種類にするかを決める必要があります。そして候補となる墓地について、永代使用料と年間管理料がどれくらいするかを調べます。
次に、どのようなお墓にするのかについて、墓石代と工事費がいくらするのかという点を確認する必要があります。特に墓石代については、材質によって価格はさまざまなので、迷ってしまいがちです。そこで事前に考えておくポイントとして、
①あらかじめ予算を決めておく
②墓の形タイプのイメージを決めておく
③良心的な石材店を選ぶ、
の3点を踏まえてお墓を選ぶようにします。ただ、民営墓地、寺院墓地の場合、あらかじめ石材店を指定されてしまう場合もあることを留意しておきましょう。
墓地選びの基本は、まずは現地に足を運ぶことが絶対条件です。交通アクセスや周辺環境、寺院墓地なら住職の人柄を確かめておきましょう。必ず自分の目で見て歩いてみて、確かめることが大切です。次に、必ずそのお墓を引き継ぐ立場になる継承者にも相談することも重要です。墓は原則として子孫に引き継がれるものであり、自分の亡き後に墓守を頼むキーパーソンの了解なくしてのお墓選びはあり得ません。最後に、その墓地の使用規約を確認しましょう。お墓を建てる期限や管理費の変動など、墓によって使用規約は異なりますので、墓地の購入前に必ず目を通すようにしましょう。
当事務所では、お墓のことでお困りのお客様に、お墓の問題を解決するためのご相談対応、墓地の選定や購入申込などの手続き支援、石材店の選定など、あなたのお墓に対する終活をサポートいたします。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合せくださいませ。
こんなに多彩 現代版お墓と納骨スタイルあれこれ
現代社会の事情からお墓に対する意識が変化してきており、従来型の先祖代々の「お墓」の形にこだわらない納骨スタイルを希望する人が増えています。従来型のお墓ではない納骨方法の選択師として、「永代供養墓」「納骨堂」「樹木葬墓地」「散骨」「手元供養」といったものがあります。
永代供養墓は、承継を必要としないお墓の総称ですが、お墓の承継者がいない人にはこちらを選択する人が増えています。また、従来型のお墓の形態にとらわれない納骨の選択肢として、「納骨堂」「樹木葬墓地」「散骨」「手元供養」といったものがあります。
永代供養墓
お墓参りしてくれる人がいない場合でもお寺が責任を持って永代に渡って供養と管理をしてくれるお墓のことを「永代供養墓」といいます。特徴としては次のとおりです。
(1)永代供養墓の納骨方法、
{C}① 最初から遺骨を骨壷から出して1箇所にまとめて土に還す、いわゆる「合祀墓
に埋葬する方法
②ある一定期間(例えば33回忌まで等)、納骨堂、納骨壇あるいは骨壷のままお骨を安置しその後合祀する方法
(2)永代供養のお墓の形態
最初から合祀される場合の合葬墓や共同墓、樹木葬墓地の形態だけでなく、33回忌までなどの一定期間、個別の納骨堂や納骨壇、あるいは骨壷のままお骨を安置し、供養されてから合祀される形態もあります。
(3)永代供養墓の費用
①永代供養料、②納骨法要のお布施、③刻字料(墓地に納骨者名を彫る費用)となりますが、一式料金で納められることが一般的です。一度必要な永代供養料を支払えば、その後の管理費、お布施などの費用が原則かからないことも特徴です(但し、年会費や維持費等が必要な場合有り)。
また、個人墓、夫婦墓と呼ばれる墓石を用いた従来型のお墓の形態であるものの、承継を前提としない永代供養墓もあります。こちらは「個人墓」、「夫婦墓」と呼ばれ、個人単位、夫婦単位でお墓に入り、一定期間、墓地管理者の管理と供養の後、合祀されるタイプの永代供養墓です。見た目は従来型の先祖代々のお墓と同じような形態ですが、建売で提供されている場合が多いのが特徴です。
納骨堂
納骨堂は、従来型の墓地に墓石を建立するというお墓の形式にとらわれず、ロッカー型、仏壇型など、従来のお墓とは異なる形式で納骨できる施設です。大半の納骨堂は、個別に参拝でき仕組みになっていて、継承も可能です。また一般的には永代使用料と管理料は必要ですが、従来型のお墓のそれと違って、比較的割安であることも特徴の一つです。さらに、お墓参りをする際、交通至便な都心にある場合が多く、この点もメリットです。
海洋散骨
海洋散骨とは、遺骨を粉末状にして、海にまく埋葬方法です。遺骨をこのように埋葬することが違法ではないか、と思われるかもしれませんが、節度を持って行う場合は、違法ではありません。一般的には、専門の業者に依頼し、散骨に適切な場所まで船で移動し散骨します。遺族だけの個別の場合と、いくつかの遺族が合同で行う散骨の場合とで料金も異なり、合同での散骨の場合の方が当然リーズナブルになります。
散骨を希望する場合は、専門の業者に事前に申込、キーパーソンにもそのことを伝え、十分に理解を得ておくことがやはり必要です。また、散骨をすると、その方を弔う墓標がないことから、遺族の理解を十分に得られるよう、散骨を希望する理由等をエンディングノートに記載しておくとよいでしょう。
樹木葬墓地
樹木葬墓地とは、墓地の敷地内に、墓標となる木を植えて、その下に遺骨を埋蔵する形式の墓地のことをいいます。樹木葬墓地の形態は実にさまざまですが、郊外に多い「里山型」と都市近郊に多い「都市型」にまず大きく分けられます。前者は、山全体などまとまった敷地が樹木葬墓地として使用され、遺骨を埋蔵するごとに植樹される「植樹型」が多くなっています。都市型の場合は、霊園の敷地の一部を樹木葬墓地として使用し、墓標となる1本~数本の樹木の周りに多くの遺骨を埋蔵する「メインツリー型」スタイルが一般的です。埋蔵方法についてもさまざまで、夫婦や家族などの単位での個別区画での埋蔵方法、他人の遺骨と一緒に合祀するタイプなどがあります。
いずれの形態でも、木の下でいずれ土に還ることができるという死生観に対する共感、散骨と異なり墓標となる樹木があるため、遺族が後々お墓参りをできることで遺族の心の拠り所を遺せること、墓地の継承者がいない場合でも利用できることなどの理由から、自然葬の形態として、今後普及していくのではないかと思います。
費用についても、従来型のお墓と比べて永代使用料や管理料も比較的安く抑えられること、墓石代等がかからないことから、樹木葬墓地のほうがリーズナブルです。
手元供養
手元供養は、遺骨全部を埋蔵せず、粉末状にして置き物の中に入れたり、ペンダントや指輪に加工して身に付けたりして故人をしのぶことができるものです。
いつも身近に故人との絆を感じることで、心が癒され前向きになれる、といった感覚から普及しています。遺骨の一部を手元供養にすることも可能なので、実際お墓を持っていても、遺骨の一部を手元に置いておきたいとの理由で、手元供養が活用されているようです。
手元供養の商品には、「加工型」と「納骨型」に分かれます。加工型は、遺骨や遺灰を特殊な機械でダイヤモンドにして、そのダイヤモンドでさらにネックレスやリングに加工します。ダイヤモンドだけでなく遺骨を石やプレートに加工するタイプもあります。「納骨型」は、遺骨や遺灰の一部を置き物などに入れて手元に置いておくもので、ミニ骨壺やロケットペンダントに入れる方法があります。また、墓地に納骨せず、自宅にそのまま遺骨を安置することも見方によっては手元供養といえます。
手元供養を希望するのは、本人ではなく、のこされた遺族である場合が多いようですので、むしろキーパーソンとなる方の意向を踏まえて、手元供養による方法を検討するということがあるかもしれません。いずれにしても今後、お墓を持たず手元供養でお墓の代わりにするという人が増えていく可能性がありますので、一つの納骨方法として検討してもよいでしょう。
当事務所では、昨多様になってきたお墓と納骨方法について、選択肢のご提案、場所の選定や申込等事務手続きの代行など、あなたのお墓についての終活全般をサポートいたします、ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合せくださいませ。
トップページに戻る
まずはお気軽にお問合せ下さい!!

初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
お墓の承継問題について
故郷のお墓を都心に移すにしても、新たなお墓を購入するにしても、そのお墓を後々まで引き継ぎ、面倒を見えてくれる人の存在があってはじめて可能なことであり、もし後々までキーパーソンが面倒を見てくれないような状況で墓を移したり、新たな墓を購入したりしても、結局は後々までその処理の問題を先送りすることになりかねません。お墓の問題を考えるにあたっては、お墓を引き継いでいく人の存在と意向を踏まえることが何より大切です。お墓を承継する人は誰かということは、次のとおり民法で規定されています。
① 祭祀主宰者による指定
② 慣習
③ 家庭裁判所の調停または審判
まずは、現在祖先の祭祀を主宰している人が後継ぎを指定することが最優先となります。具体的な指定方法としては遺言で指定することが最もおすすめの方法です。口頭での指定の場合、証拠が残らないため承継手続きがスムーズにいかず困ってしまうことになるからです。遺言に「祭祀主宰者の指定」をしておくことで、お墓の承継手続きは非常にスムーズに完了させることができます。遺言などで祭祀主宰者の指定がない場合は、慣習で祭祀主宰者は決定されます。この慣習という概念は、非常にあいまいで、結局は慣習を拠り所にしつつ、親族同士で話し合って決めるほかないことになります。この話し合いがまとまらなければ、祭祀を承継するべき方を決定するために家庭裁判所での調停を申し立て裁判所の調停で解決する方法、調停でも決まらない場合は、裁判所の審判の方法で決定するということも可能です。あなたに子どもがいない場合は、特にお墓を誰が承継するのか、前もってキーパーソンとよく話し合い、祭祀を承継してもらえることになる場合は、きちんと遺言等で指定しておくことが必要不可欠になります。
また、自分のお墓を後々守ってもらう人がいないような場合は、そもそもそれが前提となるような従来型の墓地の購入は控える選択も考えなければなりません。そのような場合は、自分のお墓についての承継の問題が生じない、永代供養や樹木葬、散骨などの方法を考えて、事前の申込を行うとともに、キーパーソンにも自分の考えを伝え、十分に理解を得ておくことが必要不可欠となります。
お墓についての終活でおさえておきたいポイント
あなたがどのお墓に入ることを希望するのか、自分の意思を明確にし、キーパーソンに伝えておくことが必要です。そもそも、あなたの先祖代々のお墓はどうなっているのかなど現状をきちんと見つめ直すことが「お墓」に対する終活の課題を考える出発点になります。そのうえで、自分がどのようなお墓に入りたいのか、その際に後々お墓の継承や既存のお墓の整理など課題を考え、必要な対策を講じていくことになります。特に、新しいお墓や納骨堂を購入するなどの場合は、その継承者となるキーパーソンに相談し理解を得ることが不可欠です。また、お墓の継承者がいない場合には、従来型の墓地の処分や永代供養墓の申込など後に遺される方の負担のないようにする必要があります。
また、散骨や樹木葬墓地、手元供養など、新しい納骨の方法を選択したい場合には、あなたなりの遺骨の処理についてキーパーソンに自分の意思を伝えて、十分に理解を得ておくことが必要です。もちろん、永代供養墓の申込や納骨堂の申込、散骨の申込など必要な手続きはあなた自身で準備しておくことが必要ですが、理想的には、あなたの亡き後それを実行してくれるキーパーソンとともにその対策を講じていくとより実現性が高まるでしょう。そして、あなたがその納骨方法を選択したことと、その理由をエンディングノートに記載し、キーパーソンを守る切り札となるように準備しておくことが必要です。
当事務所では、祭祀承継者の指定のための遺言作成のご支援、お墓についての終活にかかせないキーパーソンへの連絡調整の支援、そしてお墓についての意向を盛り込むエンディングノート作成のご支援などを通して、あなたのお墓についての終活をサポートいたします。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
トップページに戻る
まずはお気軽にお問合せ下さい!!

初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
優オフィスグループ主要メンバーのご紹介

東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優

名古屋オフィス
責任者 行政書士 冨川誠太

東京・品川オフィス
責任者 行政書士 三雲琢也

さいたまオフィス
責任者 行政書士 渡辺典和

横浜北オフィス
責任者 行政書士 深野友和

横浜南オフィス
責任者 行政書士 小幡麻里