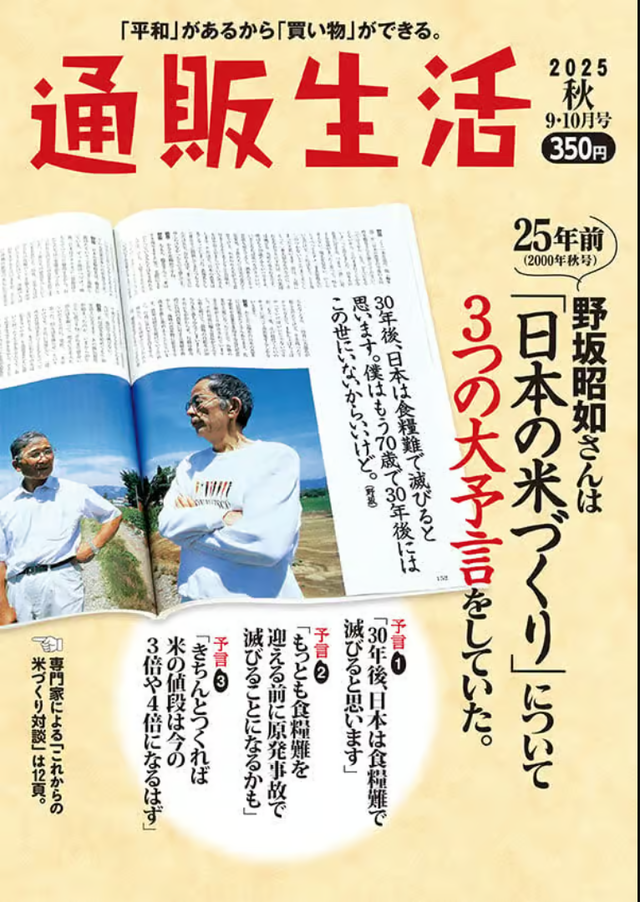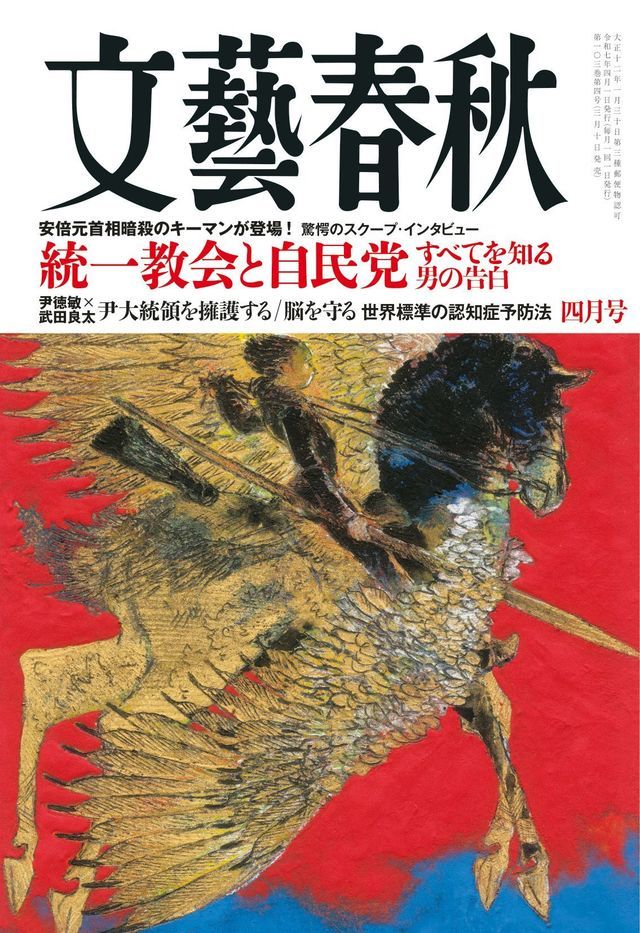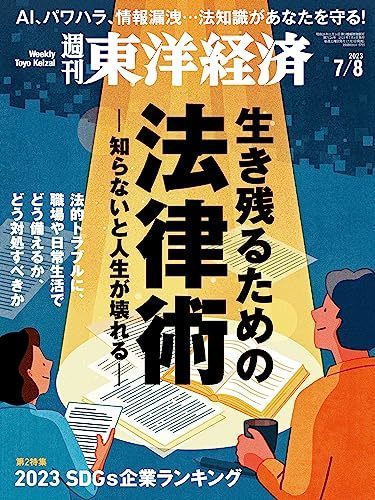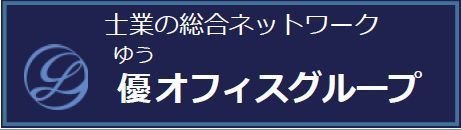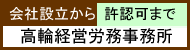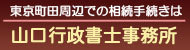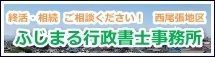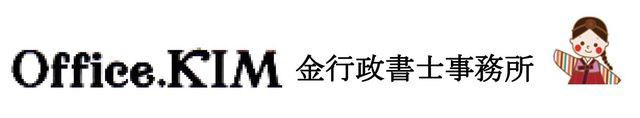相続手続代行・終活支援のことなら、東京・名古屋・横浜・さいたまの優オフィスグループにお任せください。
初回相談無料
お気軽にお問合せください
0120-928-714
事実上の相続放棄
事実上の相続放棄には「相続分の譲渡」「相続分の放棄」「特別受益による放棄」の3種類があります。趣旨、目的に応じて適切な方法を選択する必要があります。
そもそも、相続放棄は、「法律上の相続放棄」と「事実上の相続放棄」という2つに大別されます。
このうち本稿では、「事実上の相続放棄」について、解説したいと思います。
動画による解説
自分が相続人になっても、相続を放棄をすることがあります。いくつかある相続放棄の方法 のうち、今回は「事実上の相続放棄」について解説します。
<事実上の相続放棄と法律上の相続放棄の違い>
| 類型 | どんな手続き? |
事実上の相続放棄 | 相続財産を受取ることを放棄すること。 放棄内容により、「相続分の譲渡」、「相続分の放棄、」 「特別受益による放棄」の3つの方法に分かれる。 私文書を作成して行い、印鑑証明書は必要となる。 |
法律上の相続放棄 | 相続人としての地位自体を放棄すること。 相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、 家庭裁判所で手続きを行う必要がある。 |
メリット | デメリット | |||||||||
事実上の | 私文書作成と署名捺印でよく、手続きが簡単(但し、手続きの際、実印捺印が必要で、印鑑証明書は必要) | 債務の放棄はできない。 放棄の趣旨によって、作成すべき書類の内容が異なるので注意が必要。
| ||||||||
法律上の |
相続人としての権利も義務もなくなるので、借金などを負担せずすむ |
| ||||||||
当事務所では、事実上の相続放棄が必要な場面で、目的に応じた文書作成などをとおして、スムーズな相続手続きのお手伝いをさせていただいております。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
無料相談のお申込み・お問い合わせはこちら

初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
<各手続きを選択する際の注意ポイント>
放棄の内容 | 特徴 | その他の留意点 |
相続分の 譲渡 | 自分の相続分を、特定の相続人に譲渡すること。 自分の意思で他の相続人の相続分を増加できる。 以後の遺産分割協議に参加する必要がなくなり、煩わしさから解放される。 | 必ず、遺産分割協議成立前までに譲渡する必要あり。 第三者への譲渡も可能。 |
相続分の 放棄 | 単純に、相続財産を受け取る権利を辞退すること。 遺産分割協議書上で放棄の意思表示をするため、他の相続人の協議成立まで手続きが完了できない。 | 遺産分割調停の場面では、相続分放棄証書を差し入れて調停からの離脱が可能。 |
特別受益 による放棄 | 生前贈与などで財産の前渡しがあった場合に、その相続人が特別受益者の立場で放棄すること。 特別受益にあたる贈与を加味して放棄すべき額が変わるので、計算が複雑になる。 | 本来、生前贈与などを受けていないのに、相続登記を簡便に済ませるためこの方法が選択されることがあるが、事実と異なる場合、後からトラブルになる場合があるので要注意。 |
「相続分譲渡」は、自分の相続分を特定の相続人に譲渡することで、結果的に自分が相続財産を受け取る権利を放棄することです。この方法によると、自分の相続分を特定の相続人に渡すことが可能なので、被相続人のために貢献してきたような相続人に対して自分の意思で相続分を増加させることが可能となります。また、相続分譲渡証明書を作成することで、その後の遺産分割協議に参加する必要がなくなり、煩わしさから解放されるメリットもあります。
また、法定相続人ではない第三者に相続分譲渡をすることも可能で、その場合、相続分を譲り受けた第三者は。遺産分割協議に参加することができます。ただしこの場合、第三者への相続分譲渡を相続人に通知することが必要で、相続人は通知を受けてから1カ月以内に対価を支払って第三者から相続分を取り戻すことが認められていますので、注意が必要です。
「相続分の放棄」は、単に自分が相続財産を受取る権利を放棄するのみで、先述の相続分譲渡と異なり、他の相続人が遺産分割協議において誰が何を相続するのか決定されない限り、相続手続きから離脱できない煩わしさがあります。つまり、他の相続人の遺産分割協議内容に従い、さらにその協議書の中で「○○は相続財産を受け取る権利を放棄する」と明記し、署名捺印する形となります。
「特別受益による放棄」は、生前に特別受益となる贈与があった場合に、その贈与を相続分の前渡しであると相続人が認めた結果、相続時の財産の受取りを放棄するというものです。一方、実務で意外と多いのが、このような生前贈与がないにも関わらず、特別受益による放棄を承諾する書面を要求され、それに署名捺印することにより放棄手続きがなされることです。これは「特別受益証明書」と呼ばれ、これに署名捺印すると、まさに自らが被相続人から相応の生前贈与雄受けたことを前提にして放棄することになってしまうのですが、その文書の意味するところがわからないまま特別受益証明書にサインしてしまい、後から本当の意味が分かってトラブルになる場合もあります。
やはり、後々のトラブルを防止するためにも趣旨、目的に沿った、適切な放棄の方法を選択することが大切です。
相続人連絡調整・遺産分割協議書作成支援
- 相続人同士が遠方なため、相続手続きを円滑に進められるか不安
相続人と連絡が取れずに困っている
永年音信不通だった相続人と、どのように遺産分割の話を進めたらいいかわからず困っている
相続財産調査代行
- 故人の財産がどこに、いくらあるのかわからなくて困っている
遺品の中から財産がある程度わかったけど評価額が知りたい
円満に遺産分割の話をするためにもきちんと財産目録を作成したい
相続税がかかるかのかどうか心配
当事務所では、事実上の相続放棄が必要な場面で、目的に応じた文書作成などをとおして、スムーズな相続手続きのお手伝いをさせていただいております。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
無料相談のお申込み・お問い合わせはこちら

初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
優オフィスグループ主要メンバーのご紹介

東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優

名古屋オフィス
責任者 行政書士 冨川誠太

東京・品川オフィス
責任者 行政書士 三雲琢也

さいたまオフィス
責任者 行政書士 渡辺典和

横浜北オフィス
責任者 行政書士 深野友和

横浜南オフィス
責任者 行政書士 小幡麻里